【初心者必見!】あなたのサイトはどの端末からも見やすいですか?レスポンシブ対応とは、SEOで必須の「モバイル最適化」の仕組み
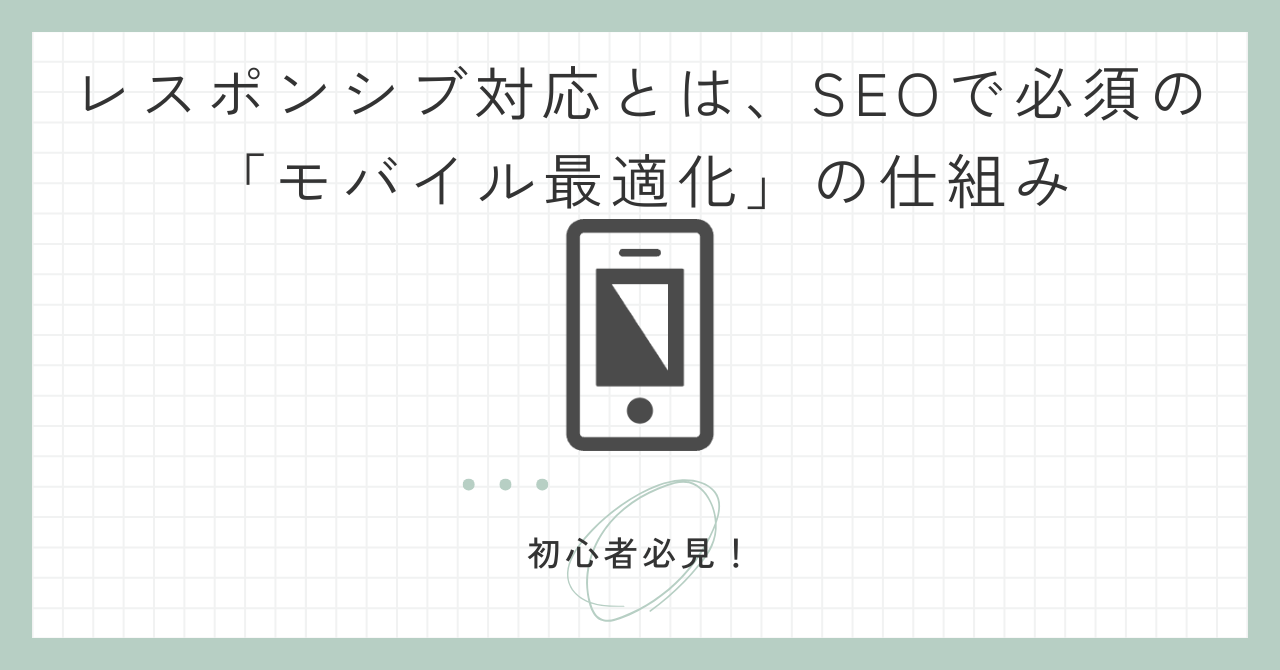
ウェブサイトを運営されている皆さん、あなたのサイトはパソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットで見たときに、きちんと最適化されて表示されているでしょうか?
現代のインターネット利用において、レスポンシブ対応は、セキュリティ対策としてのSSL化 と同様に、ウェブサイト運営に不可欠な要素となっています。
この記事では、初心者の方に向けて、レスポンシブ対応の仕組みとその必要性、そしてSEOで優位に立つための大きなメリットについて解説します。
なぜ、Webサイトの「モバイル最適化」が不可欠なのか?
現在、ユーザーはスマートフォン、タブレット、PCなど、様々なデバイスからサイトを見ています。特に、スマートフォンの急速な普及により、インターネットの閲覧はPCよりもモバイルの方が多くなりました。
総務省の調査データ(令和元年)によると、スマートフォンの保有率はPCの保有率を上回っており、個人のインターネット利用状況でも、スマートフォン(59.5%)がパソコン(48.2%)を上回っています(平成30年時点)。また、2020年の情報通信機器の保有状況においても、スマートフォンは86.8%と大多数の人が利用している状況です。
この統計データが示す通り、今やインターネットの主流はモバイルとなっており、Webサイトの管理者はモバイルからの閲覧に対応すべき状況にあるのです。モバイル対応を怠ると、レイアウトが崩れたり、ユーザーは「使いづらい」と感じてすぐに離脱してしまう 可能性があり、これはユーザビリティの低下につながります。
Webサイトを上位表示させる上で、モバイル対応は必須です。検索エンジン最大手のGoogleは、サイトの評価基準を大きく転換しました。
- モバイルフレンドリーアップデート (2015年) Googleは2015年4月に「モバイルフレンドリーアップデート」を実施しました。これは、モバイル検索において、モバイル端末に対応したページの検索順位を引き上げるというものです。レスポンシブデザインは、このモバイルフレンドリーに対応できる一つの方法だとGoogle自体が公表しています。
- モバイルファーストインデックス(MFI)への移行 さらにGoogleは2018年に「MFI(モバイルファーストインデックス)」を導入し、モバイル端末向けのWebサイトを優先してインデックス化し、評価する方針に転換しました。2021年3月からはMFIへの移行が進んでおり、モバイル最適化はGoogleのMFI全面移行に対応するために必要な措置です。
GoogleはMFIに対応するサイト構築方法として「レスポンシブデザインを採用しているサイト」を推奨しています。
スポンシブ対応とは?「画面サイズに機敏に反応する」技術
レスポンシブデザイン(Responsive Web Design)とは、ユーザーが利用するデバイスやWebブラウザに合わせ、レイアウトを「Responsive(機敏に反応)」に調整できるWebデザインのことです。これは、デバイスの画面サイズに応じて、ページのデザインやレイアウトを最適化して表示させる技術です。
レスポンシブデザインを導入すれば、「PC用」「スマートフォン用」とWebサイトを別々に作り分ける必要がありません。
Webサイトは、文章の構造化を行う「HTML」と、デザインやレイアウトを指定する「CSS(スタイルシート)」というファイルで構成されています。レスポンシブデザインでは、1つのHTMLファイルに対して、端末ごとに異なるCSSを適用し、自動的に画面表示を変更します。これにより、同じコンテンツを使いながら、スマホやパソコンで見え方を調整できます。
レスポンシブデザインを実現する鍵となるのが「メディアクエリ(Media Queries)」という機能です。
CSSファイルの中にメディアクエリを記述することで、「ウィンドウ幅が何ピクセルの時は、このような表示をする」という指示を与えることができます。これにより、デバイスのウィンドウ幅に応じて、レイアウトや文字の大きさ、ボタンの配列などが自動で切り替わるようになっています。
レスポンシブデザインのレイアウト(表示形式)には、主に以下の種類が存在します。
- レスポンシブレイアウト: 画面幅のピクセル数(ブレイクポイント)を基準にデザインが切り替わります。デバイスに応じてコンテンツを非表示設定にすることも可能です。
- リキッドレイアウト: 画面幅に合わせて要素の表示サイズが可変されるレイアウトです。どのデバイスでもすべての要素が表示されるため、同じ情報量を提供できます。
- フレキシブルレイアウト: リキッドレイアウトの発展型で、横幅の最大値を設定できます。大画面PCで閲覧した場合でも、最大値を超えると余白ができ、見やすさを維持します。
レスポンシブ対応による、SEOと運用の大きなメリット
レスポンシブデザインにすることで、ユーザーの利便性向上だけでなく、特にSEO上の大きな効果が得られます。
SEO評価で極めて有利になる
GoogleはMFI(モバイルファーストインデックス)において、レスポンシブデザインを採用しているサイトを推奨しており、レスポンシブデザインはSEO対策として欠かせない施策の一つです。
- モバイルフレンドリーを自動的にクリア レスポンシブデザインサイトを採用するだけで、Googleが重視する「モバイルフレンドリー」の評価基準をクリアできます。モバイルフレンドリーをクリアしているサイトは、検索エンジンからポジティブな評価を受けやすく、検索順位が上がりやすくなります。
- SEO評価の分散を防ぎ、有利に レスポンシブWebデザインの最大のSEOメリットは、SEO評価の分散を防げることです。デバイスごとにサイトを分けるとURLが異なり、被リンク数などのSEO評価が分散してしまいます。レスポンシブデザインであれば、URLが統一され、リンクやシェアの効果が分散しないため、SEO評価において有利になります。
- クローラーが効率的に巡回できる レスポンシブデザインは1つのURL/HTMLで複数デバイスに対応できるため、検索エンジンのクローラー(巡回プログラム)が効率的にコンテンツ情報を収集でき、Google側にメリットがあります。
ユーザビリティ(使いやすさ)が向上する
レスポンシブデザインにより、デバイスに応じて表示が最適化され、見やすさが担保されます。スマートフォンから見たときに見やすく使いやすいサイトになることでユーザビリティ(UX)が向上し、サイト離脱率が減るため、これもSEO上の効果につながります。
レスポンシブデザインは、サイト運営側の労力やコストを軽減するメリットがあります。
- 管理・メンテナンスが容易 用意するのは一つのサイトだけで、ソースコード(HTML)も一つで済むため、管理や更新、メンテナンスが楽になります。
- 制作・運用のコスト削減 PC版とモバイル版のWebサイトを別々に制作・管理する必要がないため、制作や運用のコストが抑えられ、コストの削減が実現します。
レスポンシブ対応の注意点とデメリット
レスポンシブデザインは多くのメリットがありますが、構築には注意点やデメリットも存在します。
- 初期の労力とコストがかかる:様々な端末を考慮した初期設計が必要なため、時間と労力を要し、その分サイト制作が高額になる傾向があります。
- デザインの自由度が限られる:1つのHTMLをCSSで調整するため、PCやスマートフォンでそれぞれ独自性を強く持たせるデザイン変更は難しく、デザインや表現に制約が出ます。
- 表示速度の遅延リスク:PC用の大きめのファイルやCSSコードをスマートフォンでも読み込むため、モバイル端末では表示速度が遅くなるおそれがあります。ただし、コーディングを工夫することでこのデメリットは解消可能です。
- レイアウト崩れのリスク:CSSの記述が複雑になりやすいため、記述ミスによるレイアウト崩れが発生する場合があります。
まとめ:もはやレスポンシブ対応は「ウェブサイト運営」に必須
レスポンシブデザインは、モバイルユーザーの増加とGoogleのMFI導入により、ウェブサイト運営に必須の要素となっています。
レスポンシブデザインは、ユーザーの利便性を高め、サイトの管理を容易にするだけでなく、SEO評価の分散を防ぎ、検索順位で有利に働くという大きなメリットがあります。
レスポンシブデザインはユーザビリティを向上する一つの手段であり、それ自体が目的ではありません。自社の顧客層やWebサイトの目的を総合的に考慮して判断することが大切ですが、モバイル対応はユーザビリティとSEO効果を向上させるための重要な手段であると理解し、必ず導入を検討しましょう。
データの根拠となる情報源
この記事で使用した統計データは、総務省が公表している調査に基づいています。
総務省通信利用動向調査(平成30年/令和元年)に関する記述
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/190531_1.pdf
総務省情報通信機器の世帯保有率の推移 に関する記述
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd21b110.html

